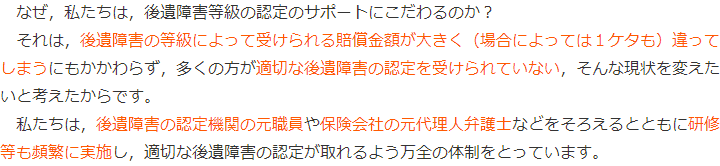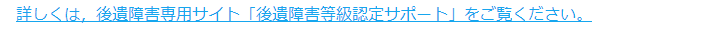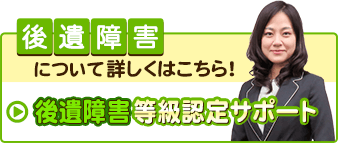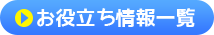後遺障害について
後遺障害申請をする場合の示談交渉について
1 治療中

後遺障害申請をする場合の示談交渉においては、治療を継続し、症状固定となり、後遺障害申請を行い、その後に示談交渉という流れになることが一般的です。
症状固定(一般的な治療方法では効果が見込めず、症状が一進一退となった状態)となるまでの治療期間については、負傷の内容、症状の経過、治療内容、医師の見解など様々な事情によって異なります。
たとえば、打撲・捻挫であれば、6か月程度で症状固定となることも多いですが、骨折となると、症状固定まで1年程度要することもあります。
また、高次脳機能障害になると、症状固定まで3年程度要することもあります。
2 症状固定
症状固定となると医師が後遺障害診断書を作成できる状況になります。
症状固定となっているかどうかは主治医の判断が尊重されますので、ご自身で判断せずに、主治医の先生とも相談しながら、後遺障害診断書の作成を依頼すべきタイミングを決めていくことが大切です。
3 後遺障害申請
後遺障害申請には、任意保険会社を経由して申請する事前認定と自賠責保険会社に申請する被害者請求がありますが、いずれにしても、損害保険料率算出機構で審査がされ、後遺障害の結果が出ます。
後遺障害申請の審査期間は負傷の内容や治療状況などによって異なりますが、一般的には、打撲・捻挫や骨折事案で1〜3か月程度、高次脳機能障害で2〜6か月程度要することが多いです。
後遺障害申請の結果に対して不服がある場合には、異議申立手続をとることもできますが、異議申立の審査は1〜3か月程度要することが多いです。
4 賠償金の計算
後遺障害申請の結果が出た場合には、後遺障害の等級に応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を計算できますので、賠償金の計算を進めて示談交渉に入っていく流れになります。
5 示談交渉
示談交渉において、弁護士に依頼している場合には、弁護士から賠償金の請求(提案)を行い、相手方任意保険会社から回答がされ、示談交渉が進んでいくことが一般的です。
相手方任意保険会社が適切な金額を回答した場合には、依頼者の方と相談のうえで、示談していくことになります。
示談が成立しない場合には、第三者機関に申立を行うか、訴訟(裁判)を提起するかなどについて、依頼者の方と相談しながら方針を決めていくことになります。